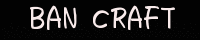花札・株札・地方札・・・
株札を入手したので、ついでに私の手持ちの地方札も。
兵庫、岡山、広島、山口周辺で使われた札「小丸」と青森、岩手を中心に東北で使われた「黒札」
そして、先日手に入れた京都、大阪、兵庫、奈良と関西を中心に使われた「株札」です。
私たちのよく知る花札は江戸時代の中期にできたデザインで、それまでは様々なデザインが存在しました。
今は任天堂・田村将軍堂・大石天狗堂さんの3社が主に製作販売を手掛けてますが、幕末から戦前までは多くのかるた屋さんが存在し、様々な札が作られ遊びも数多く存在したんですが、賭博性の高さや明治35年から平成2年まで続いた骨牌税(トランプ類税)、また昭和20年代の印刷機導入で大量生産が可能になった事から、江戸から続く手刷りの技術は衰退し、昔から続く手刷りのかるた屋は廃業に追い込まれました。
しかし、今も残る各地で使われた札のデザイン性の高さと職人の手仕事のクオリティの高さには目を見張るものがあり、ぼちぼちではありますが私は蒐集しているという訳です。
昭和まで続いたメーカーさんは何とか分かるものの、明治時代に廃業されたお店ともなると史料が少なく、小さいお店であったならなお更に知る余地も無いんですが(汗)先日、花札などのかるた収集と歴史文化を調べている方と知り合い、現在、教えを乞うている最中です。
昭和まで作られたのに遊び方が分からなくなってるってのも凄い話でしょ?(笑)
私もまだまだ知らない遊び方や各地のルールが数多く存在しますので、解明していきたいもんです、はい。。。
兵庫、岡山、広島、山口周辺で使われた札「小丸」と青森、岩手を中心に東北で使われた「黒札」
そして、先日手に入れた京都、大阪、兵庫、奈良と関西を中心に使われた「株札」です。
私たちのよく知る花札は江戸時代の中期にできたデザインで、それまでは様々なデザインが存在しました。
今は任天堂・田村将軍堂・大石天狗堂さんの3社が主に製作販売を手掛けてますが、幕末から戦前までは多くのかるた屋さんが存在し、様々な札が作られ遊びも数多く存在したんですが、賭博性の高さや明治35年から平成2年まで続いた骨牌税(トランプ類税)、また昭和20年代の印刷機導入で大量生産が可能になった事から、江戸から続く手刷りの技術は衰退し、昔から続く手刷りのかるた屋は廃業に追い込まれました。
しかし、今も残る各地で使われた札のデザイン性の高さと職人の手仕事のクオリティの高さには目を見張るものがあり、ぼちぼちではありますが私は蒐集しているという訳です。
昭和まで続いたメーカーさんは何とか分かるものの、明治時代に廃業されたお店ともなると史料が少なく、小さいお店であったならなお更に知る余地も無いんですが(汗)先日、花札などのかるた収集と歴史文化を調べている方と知り合い、現在、教えを乞うている最中です。
昭和まで作られたのに遊び方が分からなくなってるってのも凄い話でしょ?(笑)
私もまだまだ知らない遊び方や各地のルールが数多く存在しますので、解明していきたいもんです、はい。。。