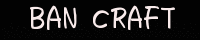興隆寺・妙見社さんにて・・・
以前、下松市にある「妙見宮・鷲頭寺」さんに行った時の事を書きましたが、今日は山口市内にある「興隆寺・妙見社」さんに行ってみました♪
興隆寺さんは、この地を治めた大内氏の氏寺で、大内氏が足利幕府から周防・長門国(現在の山口県)の守護に任じられた後、下松市にある妙見社から「妙見尊星王・みょうけんそんじょうおう」を勧請したお寺さんです。
そして、境内にある梵鐘は国指定重要文化財で、大内義隆が享禄五年(一五二三)に寄進したものです。
(重要文化財の大変貴重な鐘を突かせて頂けるんですよ。大変良い響きでした♪)
「大内氏全盛の時は非常に栄えたが、大内氏滅亡後は衰え、明治になり堂塔もなくなった。」と案内板にはありましたが、本堂の屋根の至る所に毛利家の家紋があるので、恐らく大内氏滅亡後は毛利家の庇護下の元、そして、地元の方々のご尽力で今に残ったのではないでしょうか?
一人の歴史好きとして思うのは、大内氏が信仰した妙見信仰のお寺さんは、神仏分離以前の「神仏習合」の跡が非常に色濃く残っているという事です。
例えば鳥居をくぐってお寺さんがあるとか、お寺さんの本堂の横に小さな社殿や祠があるとか。
こういうのを「摂社・せっしゃ」と言いますが、それにしても何とも不思議な作りです。
全ては想像ですが、例えば上杉謙信が毘沙門信仰や飯縄信仰にあやかろうとした様に、大内氏は妙見信仰の力で国を治めようとしたのではないでしょうか?
下松市の鷲頭寺さんも山口市の興隆寺さんも、その痕跡が色濃く残るお寺さんです。
興隆寺さんは、この地を治めた大内氏の氏寺で、大内氏が足利幕府から周防・長門国(現在の山口県)の守護に任じられた後、下松市にある妙見社から「妙見尊星王・みょうけんそんじょうおう」を勧請したお寺さんです。
そして、境内にある梵鐘は国指定重要文化財で、大内義隆が享禄五年(一五二三)に寄進したものです。
(重要文化財の大変貴重な鐘を突かせて頂けるんですよ。大変良い響きでした♪)
「大内氏全盛の時は非常に栄えたが、大内氏滅亡後は衰え、明治になり堂塔もなくなった。」と案内板にはありましたが、本堂の屋根の至る所に毛利家の家紋があるので、恐らく大内氏滅亡後は毛利家の庇護下の元、そして、地元の方々のご尽力で今に残ったのではないでしょうか?
一人の歴史好きとして思うのは、大内氏が信仰した妙見信仰のお寺さんは、神仏分離以前の「神仏習合」の跡が非常に色濃く残っているという事です。
例えば鳥居をくぐってお寺さんがあるとか、お寺さんの本堂の横に小さな社殿や祠があるとか。
こういうのを「摂社・せっしゃ」と言いますが、それにしても何とも不思議な作りです。
全ては想像ですが、例えば上杉謙信が毘沙門信仰や飯縄信仰にあやかろうとした様に、大内氏は妙見信仰の力で国を治めようとしたのではないでしょうか?
下松市の鷲頭寺さんも山口市の興隆寺さんも、その痕跡が色濃く残るお寺さんです。