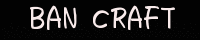先人たちの技術と知恵・・・
30年私の傍らに飾ってある「唐津 かんねどん」の土鈴。
これは佐賀県唐津市を代表する民話「勘右衛(かんね)話」の主人公・かんねどんをモチーフにした土鈴なんですけど、何だか千と千尋の神隠しでトンネル付近に置いてあった石像みたいでしょ(笑)
この「かんねどん」の土鈴が凄く好きで、あっちゃこっちゃと場所を変えたりしながらもずっと飾ってるんですが、最近、特に注目するようになったのは、土鈴が鎮座する藁の台座と頭についている藁の持ち手です。
子供の頃は随分と乱暴にいじって遊んだ記憶があるんですけど(笑)、それでも変わらない状態を保ち、むしろ経年による深みが増したようにも思えます。
先人の生活の知恵から生まれた「編む」という技術は本当に素晴らしい技術で、強度が増すと共に連続する編み目模様は、人が生み出した優れたデザインの一つだと私は思います。
革の世界でも「編む」という技術は強度を増すため、そして、デザインとしても非常に重要な技術の一つです。
そして、何かの素材を人の道具として機能させるためには、この「編む」とか「縫う」という技術は欠かせないものです。
紀元前のエジプト王朝・ピラミッドの遺品の中にレースの編物があったという事からも、「編む」という技術が如何に古くから今に引き継がれた素晴らしい技術かが分かりますよね♪
先人の知恵、先人の技術に心から敬意を表します・・・
これは佐賀県唐津市を代表する民話「勘右衛(かんね)話」の主人公・かんねどんをモチーフにした土鈴なんですけど、何だか千と千尋の神隠しでトンネル付近に置いてあった石像みたいでしょ(笑)
この「かんねどん」の土鈴が凄く好きで、あっちゃこっちゃと場所を変えたりしながらもずっと飾ってるんですが、最近、特に注目するようになったのは、土鈴が鎮座する藁の台座と頭についている藁の持ち手です。
子供の頃は随分と乱暴にいじって遊んだ記憶があるんですけど(笑)、それでも変わらない状態を保ち、むしろ経年による深みが増したようにも思えます。
先人の生活の知恵から生まれた「編む」という技術は本当に素晴らしい技術で、強度が増すと共に連続する編み目模様は、人が生み出した優れたデザインの一つだと私は思います。
革の世界でも「編む」という技術は強度を増すため、そして、デザインとしても非常に重要な技術の一つです。
そして、何かの素材を人の道具として機能させるためには、この「編む」とか「縫う」という技術は欠かせないものです。
紀元前のエジプト王朝・ピラミッドの遺品の中にレースの編物があったという事からも、「編む」という技術が如何に古くから今に引き継がれた素晴らしい技術かが分かりますよね♪
先人の知恵、先人の技術に心から敬意を表します・・・